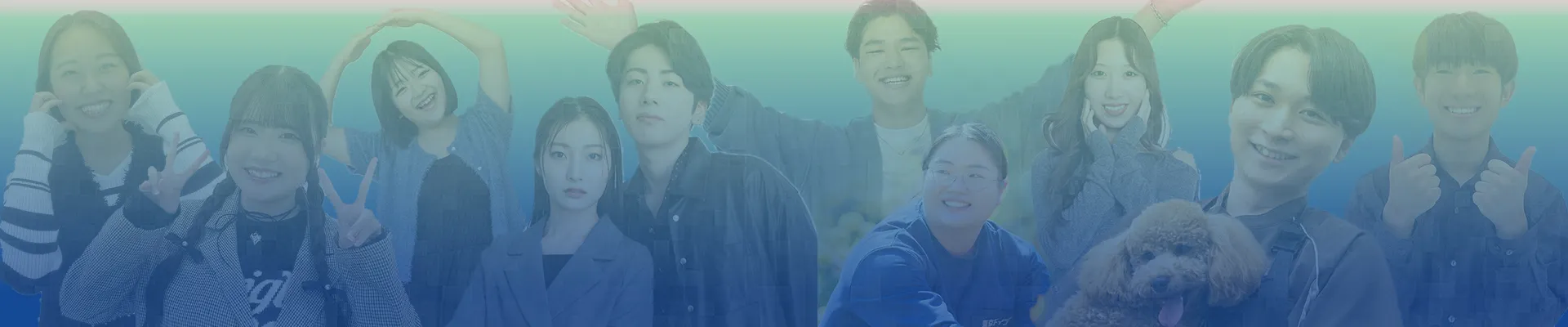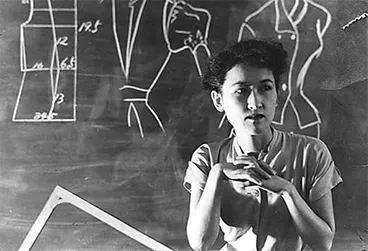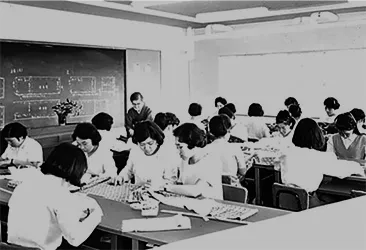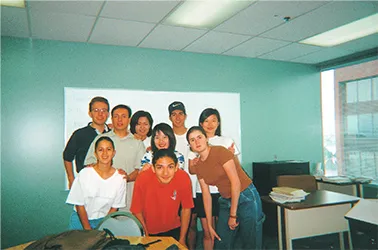「元気な学園」を育むクレド
策定ストーリーと
そこに込められた思い
2012年、本学園の理事長や役員たちから、
未来への問いかけが始まりました。
「元気な学園であり続けるために、
私たちは2020年に向けて何をすべきか?」
この問いかけが、2020プロジェクトの幕開けでした。
教職員で構成されたプロジェクトメンバーで集まり、幾度となく議論を重ねる中で、私たちの学園を語る上で欠かせないキーワードが浮かび上がりました。 それは 「元気」です。
では、なぜ「元気」なのでしょうか? 私たちの議論はそこから始まったのです。
私たちが考える「元気」には、三つの側面があります。
- 1. 元気な学生
- 2. 元気な職員
- 3. 元気な学園
- 学生たちが元気で活気に満ちていること。それが学園の顔です。学生たちに何を提供できるか。ボランティア体験や主体的企画などを通じて成功体験を積む機会を増やし、例えば東京五輪のボランティア活動をはじめ社会貢献活動への参加などが考えられました。
- 職員の元気がなければ、学生も学園も元気ではいられません。職員同士が交流できるサークル活動をつくり、プロフィールを反映させた取り組みも大切です。一人ひとりが活気を感じる職場こそが、学園全体のエネルギーを生み出す源泉となります。
- そして、学園全体が元気であるためには、教職員全員が同じ方向を向き、学園の基本方針や未来のビジョンを共有し、その「元気」を互いに支え合うことが不可欠です。
この「元気な学園」を実現するために、私たちは クレド を作るという決意に至りました。
クレドが生まれるまで
なぜ、今この学園にクレドが必要だったのでしょうか?
それは、働く仲間たち全員が明確な共通の行動指針を持ち、同じ価値観を共有し、日々の行動に落とし込めるようにするためです。
クレド策定の過程で最も重要だったのは、プロジェクトメンバー全員で意見を出し合い、共に決定していくことでした。しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。様々な意見が出され、同じ思いであっても表現が異なったりと、それらを一つの文章にまとめ上げる作業は困難を極めました。
私たちが特に意識したのは、「私は」から始まる文章にすることでした。これにより、クレドが単なる標語ではなく、一人ひとりの行動に置き換えて実践できるものになると考えたからです。完成したクレドの主語は「私たち」となりましたが、その根底には「私はどう行動するのか」という意識が強く込められています。
また、クレドの内容は、机上の空論ではなく、全員が実践できるような具体的な内容であることを目指しました。
クレドに込めた思い
私たちのクレドには、卒業生を見守るという言葉があります。この言葉は、単なる理念ではなく、卒業生との絆を大切にし、学び舎を巣立った後も彼らを支え続けるという、私たちの強い思いを表しています。
クレドの浸透とともに、学園内では教職員同士の信頼関係やステークホルダーへの配慮が深まり、それが学園の文化として着実に根付いていきました。
さらに、クレドが学園内で話題に上る機会が増えるにつれて、感謝の気持ちを伝える場面も増えてきました。学園表彰制度のような形で、日々の小さな感謝を伝え合うことができるようになったことは、私たちの大きな喜びです。